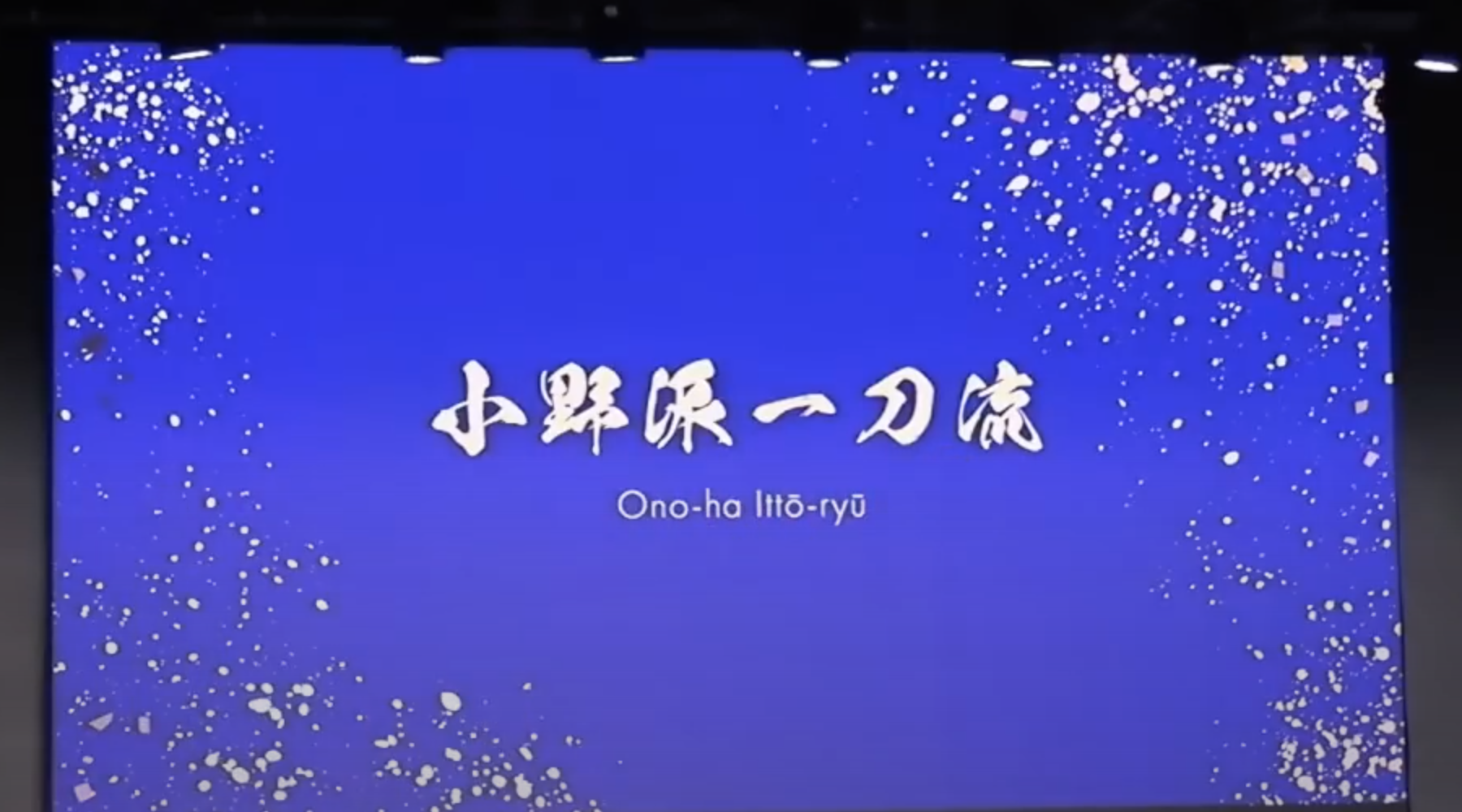小野派一刀流兵法
Onoha-Ittoryu-Heihoh流儀
Style
-
始祖・伊藤一刀斎景久は戦国期の剣客で、33回の立合で一度も遅れをとることはありませんでした。
一刀斎は師・鐘捲自齋に学び諸国遍歴の中で磨き自ら工夫を加えた剣技と哲理を弟子・小野次郎右衛門忠明に託しました。忠明は徳川家に出仕し、「一刀流」を以って武功を挙げ、後に将軍家剣術御指南役に抜擢されます。
そのお役目は代々の小野次郎右衛門が受け継ぐこととなりました。江戸時代初期には既に現在に繋がる稽古の体系が整えられ、幕末に至るまで数々の剣客を輩出しました。
-

-

-
特色は何をおいても「切り落とし」です。
当流の代名詞とも言われます。「切り落とし」は基本にして奥義。
ですから最初に学びます。ただ進み、刀を振り上げて、切り下す。
その一瞬の動作の中に四百年以上に渡り練り上げられたものが凝縮されているのです。
宗家
Head of the family
-

矢吹 裕二
- 1970年
- 福島県いわき市に生まれる。
- 1992年
- 警視庁へ入庁
- 1998年
- 第十七代宗家笹森建美に入門
- 2017年
- 本目録免許
- 2017年
- 笹森建美指名により
第十八代宗家
- 2018年
- 警視庁剣道教師拝命
- 2020年
- 一般財団法人禮楽堂代表理事
- 2024年
- 剣道八段
-
現代社会において刀剣とは最早人を斬る道具ではありません。
ではそのような無用のものがなぜ今も存在し得ているのかといえば、そこに人の心を惹きつける何かがあるからなのだと思います。
それは日本の美であると言えるのかもしれません。小野派一刀流もそれとよく似ています。
単なる人斬りの技であれば江戸時代に絶えていたことでしょう。
ところが実際は明治維新や敗戦を経てもなお命脈を保っています。
そこに人の心を惹きつける何かがあるからなのだと思います。「殺人刀・活人剣」という言葉があります。
最初は人斬りから発した技もこれを体得し自在に使うことが出来るようになれば相手を殺すことなく活かすことができる。
そこまで極めて剣を擱くことが目指すべきところです、と先代宗家はおっしゃいました。このようなもののふの心を深く蔵しているのが古武道であり、小野派一刀流です。
後世に伝え残すべき文化として日々精進怠るべからず、禮楽堂一同稽古に励んでいます。
稽古風景
-

-

-

-

流祖墓参
-

古武道演武大会
-

古武道演武大会